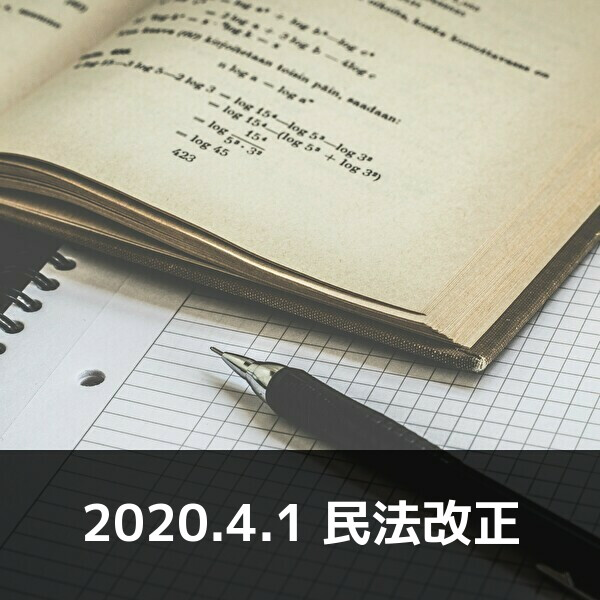債務者の帰責事由が契約解除の要件から除かれたり,不履行が軽微なものである場合には例外的に催告解除が制限されることが明文化されたり,無催告解除について,債務者に催告をして履行の機会を与えることが無意味な類型を文言上追加するなどの改正が行われました。
解除の要件
「債務者の帰責事由」不要化
| 旧法 | 新法 |
| 【541条】(履行遅滞等による解除権) 当事者の一方がその債務を履行しない場合において,相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,相手方は,契約の解除をすることができる。 |
【541条】(催告による解除) 当事者の一方がその債務を履行しない場合において,相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,相手方は,契約の解除をすることができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。 |
| 【542条】(定期行為の履行遅滞による解除権) 契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において,当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは,相手方は,前条の催告をすることなく,直ちにその契約の解除をすることができる。 |
【542条】(催告によらない解除) 2項:次に掲げる場合には,債権者は,前条の催告をすることなく,直ちに契約の一部の解除をすることができる。 |
| 【543条】(履行不能による解除権) 履行の全部又は一部が不能となったときは,債権者は,契約の解除をすることができる。ただし,その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。 |
【543条】(債権者の責めに帰すべき事由による場合) 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,債権者は,前二条の規定による契約の解除をすることができない。 |
旧法下においては,債務不履行について債務者に帰責事由がある場合でなければ,債権者は契約を解除することができないと解されていました。
しかし,新法では,債務不履行につき債務者に帰責事由がなくても,債権者が契約を解除できることとし,例外的に,信義則及び公平の観点から,債務不履行につき債権者に帰責事由がある場合には解除権行使が制限されることになりました(新法§541ないし§543)。
このように債務不履行解除の要件から債務者の帰責事由の存在を除外した理由は次のように説明されています。
① 債務不履行があったにもかかわらず,債務者に帰責事由がなければ,契約を解除することができないとすると,債権者は,なおも契約に拘束され続けるため,例えば,天災等により,債務の履行の目途がたたない状況であっても,当該契約に代えて,別の取引先と同様の契約を締結し,債務の履行を受けるといった対応をとりづらい。
② 解除制度を,(債務の履行を怠った債務者に制裁を課す制度ではなく,)債務の履行を得られない債権者を契約の拘束力から解放する制度と考える場合,債務不履行解除に債務者の帰責事由の存在を要求することは論理的帰結とはいえない。

「解除に債務者の帰責事由不要」,ここテストに出ます!
催告解除
当事者の一方がその債務を履行しない場合において,相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,相手方は,契約の解除をすることができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
変更点
判例(大判昭和14年12月13日,最判昭和36年11月21日)を踏まえ,催告解除について,債務不履行がその契約や取引上の社会通念に照らして軽微であるときは契約を解除することができない旨の規定が新設されました(新法§541但書)。
このように債務不履行が軽微であるかどうかは,「契約や取引上の社会通念に照らして」判断されることになりますが,具体的には,その不履行が債権者に与える不利益や当該契約の目的達成に与える影響が軽微であるかどうかなどを考慮して判断します。
また,軽微性の判断は,契約書の文言のみならず,当該契約に関する一切の事情をもとに,当該契約についての取引上の社会通念も考慮して,総合的になされるため,たとえ契約書で一定の事由を解除事由として規定し,当該事由に該当する不履行が発生したとしても,それをもって,直ちに催告解除が認められるわけではありません。当該事由に該当する不履行が,契約の性質・目的,契約締結に至る経緯,当該契約についての取引上の社会通念に照らして軽微であると判断されるのであれば,催告解除が制限されるということもあります。
要件事実
なお,不履行の軽微性(新法§541但書)を基礎付ける具体的事実は,契約解除の主張をした時点で,通常現れるので,不履行が軽微であると認められる場合には,再抗弁で不履行の軽微性を基礎付ける具体的事実を主張するまでもなく,契約解除の主張は主張自体失当になります。
(例えば,リンゴ100個の売買契約を締結したものの,売主がリンゴ1個を納品しなかったケースにおいて,買主が未納であるリンゴ1個を引き渡すよう催告したが履行がないことを理由として契約解除の主張をした場合,当該主張をした時点で不履行が軽微であることは現れています。)
以下では,催告解除が抗弁として主張される場合を想定します。
まず,催告解除の実体法上の要件は,
です。
では,これら㋐~㋗のうち,どれが催告解除の要件事実になるのでしょうか。
まず,㋐については,通常,請求原因で現れるので,抗弁で改めて主張立証する必要はありません。
次に,㋑については,債務は通常は履行が可能なものなので,履行が不可能であれば,そのことを債務者が再抗弁で主張立証すべきであると考えられています。
㋒については,新法§412各項に定めがありますが,期限の定めのない債務であれば,「催告」により「遅滞」が基礎付けられます(新法§412Ⅲ)。
㋓については,弁済が債務消滅の要件事実であることに鑑み,履行によって債務を免れ,利益を受ける債務者が再抗弁で「債務を履行したこと」を主張立証すべきであると考えられています。
㋔については,債務が存在すれば履行されるのが通常で,履行遅滞が生じている場合には原則として違法性が肯定されるため,債務者が再抗弁で「違法性のないこと」を主張立証すべきであると考えられています。
ただし,売買契約等の双務契約の場合は違います。双務契約の場合には,契約当事者は相互に同時履行の抗弁権(新法§533)を有しているため,一方当事者が自己の債務の履行の提供をするか,相手方当事者の債務が先履行でない限り,相手方当事者がその債務を履行しないことは違法になりません。すなわち,同時履行の抗弁権の存在は,履行遅滞の違法性阻却事由として機能しているのです。そこで,催告解除を主張する者としては,このような同時履行の抗弁の存在効果を消滅させるために,催告に先立って自己の債務の履行の提供を行ったか,相手方当事者の債務につき先履行の合意がなされたことを主張立証する必要があります。
なお,履行の提供は,一度なされれば,同時履行の抗弁権の存在効果は消滅するため,継続して行う必要はありません。
㋕の催告については,付遅滞のための「催告」(新法§412Ⅲ)も兼ねることができるので,付遅滞のために別途催告を主張立証する必要はなく,1回催告が行われたことが主張立証されれば十分です。
なお,催告後,客観的に相当期間が経過したと認められれば,解除することができるので,催告にあたり,期間を定めてしたことは要件事実になりません。
以上より,㋒,㋕,㋖,㋗(双務契約の場合は㋔も)が要件事実となります。
無催告解除
1項:次に掲げる場合には,債権者は,前条の催告をすることなく,直ちに契約の解除をすることができる。
① 債務の全部の履行が不能であるとき。
② 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
③ 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
④ 契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において,債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑤ 前各号に掲げる場合のほか,債務者がその債務の履行をせず,債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2項:次に掲げる場合には,債権者は,前条の催告をすることなく,直ちに契約の一部の解除をすることができる。
① 債務の一部の履行が不能であるとき。
② 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
変更点
旧法では,契約全部の無催告解除を行える場合として,旧法に明文の規定があった①履行不能の場合や②定期行為の履行遅滞の場合が明文で定められていました。
しかし,催告をして,債務者に債務の履行の機会を与えても意味がない場合は,①や②の場合に限られません。
そこで,新法では,債務者に債務の履行の機会を与えても意味がない場合として,新たに③債務者が履行拒絶の意思を明確に表示した場合や④契約目的を達するのに足りる履行の見込みがないことが明らかな場合,⑤債務の一部が履行不能に陥るなどし,残存部分のみでは契約目的を達することができない場合が加えられました(新法§542Ⅰ)。
また,同条Ⅱにおいて,①債務の一部が履行不能である場合,②債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合に,契約の当該一部の無催告解除を認める旨の規定も加えられました。
要件事実
原状回復義務の範囲
| 旧法 | 新法 |
|
【545条】(解除の効果) 2項:前項本文の場合において,金銭を返還するときは,その受領の時から利息を付さなければならない。 3項:解除権の行使は,損害賠償の請求を妨げない。 |
【545条】(解除の効果) 2項:前項本文の場合において,金銭を返還するときは,その受領の時から利息を付さなければならない。 3項:第一項本文の場合において,金銭以外の物を返還するときは,その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。 4項:解除権の行使は,損害賠償の請求を妨げない。 |
契約の解除によって契約当事者が負うことになる原状回復義務について,新法では,一般的な解釈に従い,金銭を返還する場合だけではなく(新法§545Ⅱ参照),金銭以外の物を返還する場合についても規定を設け,受領時以後に生じた果実をも返還する義務を負うこととされました(同条Ⅲ)。
解除権消滅の要件
| 旧法 | 新法 |
|
【548条】(解除権者の行為等による解除権の消滅) 2項:契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し,又は損傷したときは,解除権は,消滅しない。 |
【548条】(解除権者の故意による目的物の損壊等による解除権の消滅) 解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し,若しくは返還することができなくなったとき,又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは,解除権は,消滅する。ただし,解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは,この限りでない。 |
変更点
旧法§548Ⅰは,解除権者が「自己の行為」又は「過失」により契約の目的物を著しく損傷するなどしたときには解除権は消滅すると定めていました。
しかし,新法では,解除権者が予測に反して解除権を失わないようにするため,例外的に,損傷等の時において解除権者が解除権を有することを知らなかったときには,解除権が消滅しないものとしています(新法§548但書)。
また,解除権の消滅の要件を明確にするため,一般的な解釈に従い,上記の「自己の行為」との要件を「故意」に改めています(同条本文)。
さらに,旧法§548Ⅱは削除されました。同項は,確認的な意義を有するに過ぎない規定であり,かつ,解除権が消滅しない場面を網羅しない点でかえって有害であると考えられたためです。
要件事実
準備中。
確認問題〔契約の解除〕
新法に基づいて回答してください!(全3問)